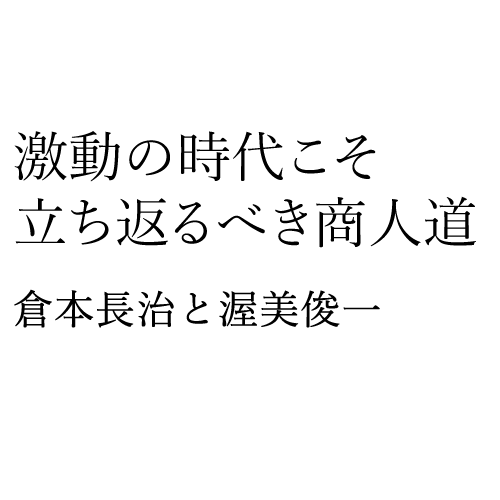月刊マーチャンダイジング読者の方々でも「渥美俊一」の名前は知っていても「倉本長治(くらもとちょうじ)」の名前を知っている人は限られるだろう。 戦後日本の商業発展のうえで、特筆すべき2人の商業経営指導家…こう書くと単なる現代のいわゆる「経営コンサルタント」の類として一括りにされてしまうのかもしれないが、この2人はそのような分類ではとうてい収まりきるものではない。
この2人の出会いこそが現在まで連綿と続く「チェーンストア産業づくり=商業の基幹産業化」を発現せしめ、その理論的、技術的、そして理論的支柱となって数多の経営者、従業員たちを鼓舞し続けたのである。
思い切った言い方をすれば、ドラッグストア(DgS)企業のベースとなる多店舗経営の基礎理論を実証的かつ統合的に築いてきたのが渥美俊一であり、DgSが何のために存在するのか、社会的な意義、商業経営の根本思想を説いたのが倉本長治であった。
渥美俊一は倉本長治を生涯師と仰いだ。2人の出会いの妙をたどってみよう。
「店は客のためにある」 ─倉本長治とは何者か?
倉本長治は1899年(明治32年)東京の芝に生まれ、仙台二中を経て山下汽船に入社し、その後香港に赴任。第一次大戦の空前の好景気の中、倉本長治は海運を通して世界の一端に触れることになる。 その後、東京商業会議所(現東京商工会議所)の調査課に勤務。このころ商業経営雑誌『商店界』(誠文堂新光社)に寄稿をはじめ、1925年(大正14年)には『商店界』編集長に迎えられ、商業とのかかわりがより増すことになった。 翌年には後の商業界ゼミナールの原型とも言える商店経営者を集めた「商店実務講習会」を実施。単なる経営情報の集積にとどまらず、理論と実践の場を提供するというモデルを作り上げ推進していった。
太平洋戦争終結後、倉本は不運にも、専務を務めていた出版元が、統制経済下で国策雑誌を発行していた関係から、GHQによる公職追放の憂き目にあう。 しかし『商店界』時代に蓄積していた全国小売店主との関係性から戦後の荒廃した国土のなかで、再び瓦礫の中から立ち上がろうとしていた志高い商人の招きを受けて全国を行脚、都度経営指導に応じた。 1948年(昭和23年)新たな商業勃興を志した有志たちによって『商業界』が発刊。その2年後追放が解けた倉本は商業界主幹として迎えられ、ようやく再び商業経営理論と実践の情報発信の第一線に復帰した。このとき倉本は51歳。長い雌伏を経て、温めていた構想が矢継ぎ早に打ち出され、翌年には第1回商業界ゼミナールが開催されている。 1953年(昭和28年)にははやくも第1回商業界主催のアメリカ視察団を派遣している。これも若き日に海運を志し、世界を体感した経験から発せられたことは想像に難くない。
その後商業界は昭和30年代にアメリカ視察ツアーを定番化し、新しい経営を志向する若き商店主たちにアメリカで勃興期を経て成長期を迎えつつあったスーパーマーケットとショッピングセンターの実際を見せ、一方で商業界ゼミナールという膝を突き合わせた商人の勉強道場で、最新理論の移植と検証をしつつ、商人とはいかに生きるべきかという根本思想の種をまいた。最新理論の実践には、それをやりぬくための土台の構築-それはお客のためになるのか、ひいては社会にとって有益なのか、という問いかけに常に立ち返る必要があることを見抜いていたからである。 「店は客のためにある」には続きがある。
「店員とともに栄え、店主とともに滅びる」。 店は客と従業員の信頼の上に成り立ち、店主の考え方ひとつで簡単に消え去ってしまう。倉本の晩年は、石門心学などひたすら商人道の研究と流布に尽力した。
「古くして新しきもののみ 永遠に不滅」
商業界ゼミナール初期のスター講師であった倉本の同友新保民八(しんぼたみはち)は、はじめて箱根に登り首をかしげる商店主たちにときに壇上から激烈なメッセージを放ったという。 新保は商業界ゼミナールの根本思想を表現した名言を遺している。「正しきによりて滅びる店あれば、滅びても良し、断じて滅びず。古くして古きもの滅ぶ、新しくして新しきもの滅ぶ、古くして新しきもののみ永遠に不滅」 既存商業がデジタル革命にあって変革が迫られる中でも普遍の真理をいまに伝えている。
昭和20年代後半から30年代の商業界ゼミナールにはどのような人物が参加していたのだろうか。
ダイエー創業者中内功は、昭和30年代前半からゼミナールに参加している。 そもそもは、雑誌『商業界』誌上で「大阪で薬を安売りしているけしからんやつがいる。薬は人命にかかわる神聖なもので大根や菜っ葉みたいに安売りするとはけしからん」という記事を読んで憤慨した中内が文句を言いに行ってやろうと箱根にきたのが最初である。
実際は、その記事は倉本が書いたものではなく、「薬も食も人間の口から入って美と健康にかかわる大事なもの、両者になんら差もない」という中内の主張を、倉本は全面的に同意し、ゼミナールで共有の概念として紹介した。中内もまた「もみ手をしてお客様にありがとうございましたというだけの商人像から脱皮せよ」という倉本の革新商人論に眼からうろこが落ちたという 後にジャスコとなるオカダヤの岡田卓也、フタギの二木英徳、コメリの捧賢一、六花亭製菓の小田豊四郎、平和堂の夏原平次郎、紅丸商事(ヨークベニマル)の大高善兵衛も父と箱根の山に登った。
ヒグチ産業(薬のひぐち)の樋口俊夫、ミスターマックスの平野比左志、ナフコの深町勝義、西松屋チェーンの茂理佳宏、ダスキンの鈴木清一、駒井茂春といった人々もゼミナールで懸命に勉強した。 ゼミナールは、商人たちの勉強の場であるのと同時に、自然と同志を募りあう場でもあった。ゼミナールでの出会いが、後にいくつもの巨大な流通グループを形成していく淵源となったことも忘れてはならないだろう。
「共有の冒険へ」 ─遺志を受け継ぐもの
商業界ゼミナールというひとつの熱い魂のようなものに導かれて、一人のエリート然とした青年記者が取材に訪れる。 渥美俊一。1926年(大正15年)三重県松阪に生まれ、旧制津中学、旧制一高を経て東大法学部を卒業後、1952年(昭和27年)読売新聞社に入社。横浜支局で横浜港からアメリカに続々と物資が積み込まれていく船をみて、アメリカに見たこともないような巨大な商業店舗があることを知る。
1958年(昭和33年)東京本社勤務に戻ると、渥美は週1回「商店のページ」を担当する。当時新進気鋭の商店経営者たちを訪ねて繁盛ぶりを紹介する記事だったが、渥美は取材により蓄積された商店経営を体系化していった。この「商店のページ」は全国の熱心な商人たちに知られるようになる。
第3回商業界ゼミナールから講師を務めていた当時新潟大学で商業経営を論じていた川崎進一は、昭和33年箱根に取材にやってきた渥美との出会いをこう述懐している。
「渥美記者は大学教授であった私がリアルな商店主たちに経営計数を教えていたことに対してその目的はなにか?倉本長治のいう『店は客のためにある』というテーゼも受講者にその理念がよく理解され浸透していくためには、たんに自己中心の行為を正当化するスローガンにしかならないのではないか、それを実現する制度、社会システムを作り上げる必要があるのではないか、ということを鋭く問うてきた。これは一本とられたなと。流通業、小売業全体を見据えて、教育目的を考えて講義するということを私も考えていなかったわけですから」 渥美は、最後に「わが国の後進的な小売業態に欠けているものは何ですか?」ときく。川崎は「それはチェーンストアではないですか」と返答した。渥美はようやく同感の微笑をみせたという。
渥美は、商業界ゼミナールという倉本、川崎という先達に出会い、ぺガスクラブを結成、商業界ゼミナールの看板講師として長く登壇した。革新的思索を社会的な仕事に昇華し、志を同じくする数多の商店主たちを共有の冒険に駆り出したのである。
むすび─青山と白雲
月刊MDの若い読者に知っていただきたいのは、激動の時代こそ、古きを識り、新しくを行う大切さであり、それは人と人との「出会い」から生じるということである。
旧渥美俊一邸(現ニトリ渥美俊一記念館」には倉本長治から渥美俊一に贈られた「白雲自去来」の軸がかかっている。 これは禅のことばだ。もとは「青山元不動 白雲自去来」という対句である。白い雲は自ら雲を集めて小さくも大きくもなり、どこへでも飛べる-倉本長治は、商業発展の新たな社会的仕事に取り組もうとした渥美に大事を成すには雲(志を同じくする仲間)を呼び集める力がなければならない、しかしそれはときに攻撃され、ときに勢いに乗じる。でもそれは動かざる青山(=徳)と一対であれば、小さくも大きくもそれなりに趣のある絵となるだろう」という意味をこめたものではないか。まさに青山と白雲こそは2人を象徴しているように思われる。
■参考文献
「みち楽し」倉本長治 商業界
「商業界別冊 倉本長治主幹追悼写真集」商業界
「チェーンストアの産業化ーペガサスクラブ25周年記念特集ー」(『経営情報』日本リテイリングセンター
「チェーンストア産業づくり決起大会ーペガサスクラブ活動30周年記念特集ー」(『経営情報』日本リテイリングセンター
(初出 月刊マーチャンダイジング2020)